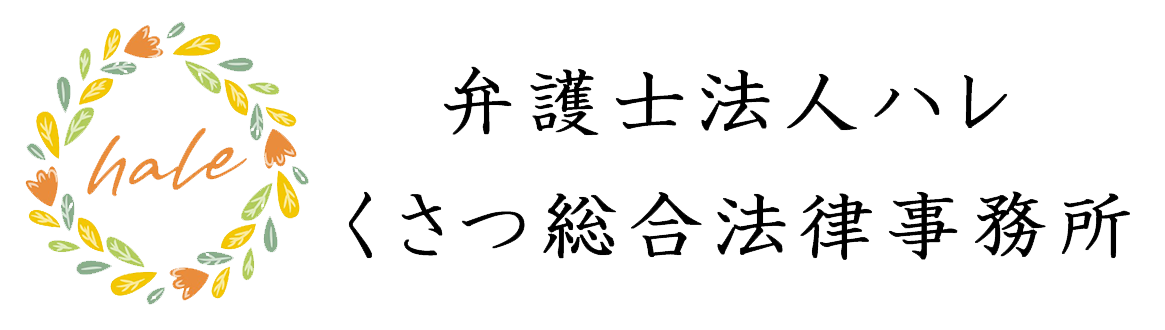家族絶縁後に発覚した母から妹への生前贈与と
父による預金引き出しの遺留分の争いがあった事例
依頼者:50代 性別 男性
相談前
相談者Aさん(長男)は、母親が亡くなった後に遺産分割について調査を開始し、以下の事実が判明しました。
1. 母親は生前に妹Bさんへ所有するマンション(評価額3000万円)を譲渡していた。
2. 母親名義の現金預金は約600万円程度しか残されていなかった。
3. 父親Cさん(存命)は母親の預金を管理しており、生前に大半の預金を引き出していた可能性がある。
4. Aさんは母親が存命中から父親および妹Bさんとの関係が悪化し、家族から事実上絶縁されていた。
Aさんは、母親の財産が不公平に処分され、自身の遺留分が侵害されていると考え、法的対応を希望して相談に来ました。また、そもそも母親は認知症であったため、マンションの譲渡や生前の引き出しは母親の意思に基づくものなのか非常に怪しいと考えていました。
相談内容
Aさんは、母親の遺留分に相当する額を確保したいと考えていましたが、妹Bさんが生前贈与を受け、父親Cさんが預金を引き出していたことで、どのように請求を進めるべきか悩んでいました。
弁護士の対応
●遺産状況の調査
不動産登記簿を確認し、マンションが母親から妹Bさんに生前贈与されたことを確認しました。さらに、司法書士がついており、所有権移転登記がなされていたことが判明しました。これらの詳細は登記簿謄本だけでは確認できず閲覧は無制限にできるわけではないため、法務局に閲覧の必要性を疎明して閲覧をしたという経緯があります。
母親名義の預金口座の取引履歴を調査し、父親Cさんが約1500万円を引き出していた事実を突き止めました。
母親の死亡時点での遺産総額を算定(マンション3000万円+現金600万円=3600万円)。ただし、上記の1500万円の使途不明金が遺産に組み込まれる可能性があるので、この遺産はミニマムとしての見積でした。最大でいうと5100万円の遺産がありました(使途不明金が絡む遺産分割についてはここが一番難しいところです。)。
●遺留分の計算
母親の相続人は、父親Cさんと子ども2人(AさんとBさん)。
法定相続分は、父親1/2、子ども2人で各1/4。
Aさんの遺留分割合は、法定相続分1/4の1/2=1/8。
遺産総額3600万円×1/8=450万円がAさんの遺留分で5100万円とした場合は637.5万円となります。
●法的主張と請求内容
生前贈与されたマンション(3000万円)を遺留分算定の基礎財産に含めるべきと主張。
預金引き出しについては、父親Cさんによる個人的な利用の可能性を追及。
両者に対して遺留分侵害額の支払いを請求する内容証明郵便を送付するとともに、調停を申立しました。
●交渉と調停
妹Bさんは「母親が生前に意思をもって譲渡したもの」であり返せない、住む場所が無くなると反論。
弁護士は、生前贈与が遺留分侵害額請求の対象になる法的根拠を丁寧に説明し、金銭的な支払いで構わない旨を説明しました。
父親Cさんに対しては、預金引き出しの使途に関する説明を求め、不透明な支出分について返還請求の可能性を示唆。
調停を通じて双方の妥協点を模索。
●和解案の成立
互いに一定の譲歩をして父・妹から合わせて遺留分相当額の600万円をいただくことで合意しました。計算上の遺留分が最大で645万だとすると早く終わる分合理的な金額であろうということで合意しました。
●解決の結果
遺留分相当額である600万円を一括で支払ってもらいました。
弁護士から一言
性格が非常に変わった父親との関係や、その父親がとても可愛がっていた妹との関係について、お悩みになられた末にご相談を頂き、代理人に就任しました。就任直後は父親の連絡が来ており非常に苦慮致しましたが、相手方に代理人が就任してからは比較的スムーズに話合いが進められました。結果的には遺留分額を十分に受け取ることができ、ご満足いただけたようで良かったと思います。